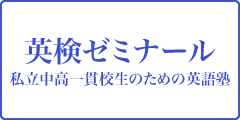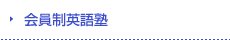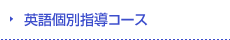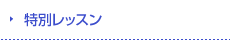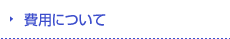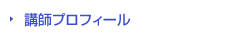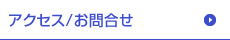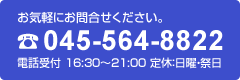Category
Archive

日常の中の外国語(2)
日常の中の外国語(2)
前回の「日常の中の外国語(1)」では、いわゆる西暦を表すA. D. やNo. さらにa.m. p.m. が、全てラテン語であることを確認済み。
今回は、ドイツ語とフランス語を代表して、より卑近な例として「アルバイト」、「サボる」を取り上げてみよう。
カタカナに化けているので、正体を見極めるのは難しい。私たちの悪い癖でカタカナは何でも英語であると思いがちであるので慎重に。
1) アルバイト
「アルバイト」は、ドイツ語の名詞Arbeit をその読み通りカタカナにしたもの。Arbeitは、「仕事、労働」の意味で、英語のworkに相当する。接尾辞を付けてarbeiten(働く)とし、人称接尾辞を変化させれば動詞として機能する。
英語で「アルバイト」は、part-time jobが一般的。part-timeを副詞として、work part-time(アルバイトをする)とも言う。他に、moonlight(アルバイトする)などの表現もある。
2) サボる
「サボる」は、フランス語のsabotageという単語の前半部分「サボ-」
と日本語の動詞を形成するための造語要素
「-る」で作られている。
sabotageは、「故意に仕事をぞんざいに行なったり、仕事に欠かせない機械を破損させたりして経営者側にダメージを与えること」を意味する。
この造語が日本で使用され始めた当時、なんらかの理由で、sabotage というフランス語が新鮮であったのであろう。
造語要素後半の「〜る」は、繁殖力旺盛な造語要素なので日本語の単語が日々生まれている。以下、英単語の要素と「〜る」の組み合わせを見てみよう。
「ググる」<google
「ディスる」<disrespect
「バグる」<bug
「パニクる」<panic
次に、日本語要素+「〜る」を眺めてみよう。
「事故る」
「こくる」
「拒否る」
「愚痴る」
他にもたくさんあり、自分で作って使ってみると良い。たとえば、ネット的には「メリカる」、「アマゾる」、「ウィキる」など。食事的には、「マックる」、「スタバる」、「ドトる」など。
言葉は使うことに意義がある。今、使われている言葉は新鮮であり、それゆえにその言葉はすぐに痛み、腐り、廃れていく。
だからこそ、地域別に、また古代などに使用された言語の研究が人々の生活や思考法を探る最大の手掛かりになり、そこに今では失われた大切な知恵を見つけることができるかもしれない。
同時に今、私たちが使っている日本語は100年後、200年後には死語だらけになっていて、専門の辞書がなければ解読不能にっているかもしれない。または日本語が絶滅危惧言語になっている可能性もある。それに伴い日本人という概念も相当に変化しているであろう。
日常の中のラテン語(1)
日常の中のラテン語(1)
たとえば、Mr. という英単語があり、なぜピリオドが付いているのかと質問されたら長い単語を縮めた場合、つまりMisterを初めの文字(M)と最後の文字(r)、さらにピリオド(. )で表記することができると答えることになるであろう。
2、3の例も忘れずにつけ加えよう。
Dr.はdoctorであり、発音が異なるので注意が必要だがMrs.はMistressの短縮形であり、極め付けは最もよく使われる英単語の記号No.(ナンバー)はnumberであり….これは理論的にNr. になるはずであるが…..
注)Ms.は、既婚、未婚を問わない表記として1950年代に使用され始め、その後1970年代に男性を表記するMr.と対置する位置付けとして女性運動によって推奨されるようになる。
No. は、ラテン語のnumeroの略語である。ラテン語で「数」という単語はnumerusという形が辞書には載っているが、辞書に記載されている形は主格であり、意味は「数は」となる。numeroは奪格であり、「数において」くらいの意味になる。
もちろん発音は異なり、アクセント記号が付くが、フランス語ではnuméroをそのまま使っている。
詳しい説明は省くが、ラテン語では全ての名詞が、英語のI, my, meのように変化する。これは不便そうに思えるけれど、こうした方が「〜は」「〜の」「〜を」「〜に」「〜で」とかを簡単に表現でき便利であるとも言える。このようなシステムを格変化と言う。
ドイツ語やロシア語を第二外国語として学ばれた方は、この格変化の理解・暗記の悪戦苦闘の記憶が蘇るであろう。
先に考察したNo.(ナンバー)のように、実は日常生活の中でラテン語は影を潜めてはいるが主要なポジションで多く活躍している。
日常生活の言語的主要ポジションといえばやはり時システムであろう。
紀元前はB. C. と表すけれど、これは英語であり Before Christの短縮。A. D. がラテン語。
2021年という表記は「西暦」であり、これはイエス・キリストという人が生まれた年を西暦1年と数えて、今年が2021年目であることを示している。この時システムはA. D. で示される。Anno Domini(主の年において)というラテン語の略語である。
前半のanno は、anniversary(1年に1回巡ってくるもの)に含まれているものと同じ、後半のdomini はdominant(支配的な)などの英単語にその痕跡が認められる。
A. D. は、主であるイエスが生まれてからの年を表している。しかし実際には、イエスという人は西暦元年より4年くらい前に生まれていると推定されている。
現実とそれを表す言葉とのギャップがあり、今年が「西暦2021年」というのは相当に間違っていることになるが今更修復は困難であろう。一度動き出した大型船は後には戻れない。
ところで、タイやラオス、カンボジアなどに行くと、今年は2564年であると言われる。これはお釈迦様が入滅した年を仏暦1年と数える「仏暦」を採用しているからである。
計算方法は、西暦に543年を足すと仏暦になると覚えておけばよい。タイ語では、仏暦は「ポォーソォー」、西暦は「コォーソォー」という。
さて、あと少しだけ時関係のラテン語の略語を眺めてみよう。
a.m. は、ante meridiem
p. m. は、post meridiem
anteは「前」の意味で、postは「後」の意味、meridiemは「昼」の意味だから、a. m. とp. m. は、ちょうど日本語の「午前」と「午後」に相当する。
時に関係するラテン語は、月を表す語にも生きている。JulyはJulius Caesar(ユリウス・カエサル)の名に因んだものであるし、Augustはもちろん初代ローマ皇帝Augustus(アウグストゥス)でる。
ほんとうはOctoberは「8月」であり、それはoctopus(タコ)が「octo8本+pus足」であり、octave(オクターブ)が「8度音程」である ことで納得できるかも知れない。
同様にDecemberが本来「10月」であるのは、decade(10年間)やdecimal system(十進法)という英単語を想起すればよい。この辺の事情についてはHP内のブログLINGUA MANIAの初めの方にJuly for Julius
Caesarというタイトルで以前書いたことがあるので、興味のある方は覗いてみてください。
『不滅のあなたへ』
『不滅のあなたへ』
私たちの「心」的なものを表す言葉に「精神」と「魂」というのがあり、それぞれに「神」や「鬼」が含まれていて、改めて見つめるとなにやら怖い感じもする。私たちの体には「神」が閉じ込められているのだろうか、それとも「鬼」?
英語で「精神」はspirit。この語は、ラテン語のspiritus(息)にその源がある。神が生命に「息」を吹き込んで、人間を作ったというのがよくある説明である。
日本語の「息」と「生きる」も無関係ではないであろう。
マルクス・アウレリウス(古代ローマの皇帝で、五賢帝の1人)の『自省録』を読むと*「ダイモーン」という言葉に度々遭遇する。訳者によっては、この「ダイモーン」を「魂」「鬼神」「神霊」などと翻訳する人もいる。
*ダイモーン:神と人間の中間にある存在で、各人間にとっての守護霊となる。エピクテトスは、これを各人の理性と同等のものとみなしている。
やや複雑な時代背景を省略するが、キリスト教の影響のもとに、このダイモーンはその後に「デーモン」となり「悪魔」にされてしまった。
キリスト教は、一神教なので、他の宗教の神を一切認めない。したがって自分の神以外を「悪い神」→「悪魔」として追いやってしまった経緯がある。
映画『エクソシスト』に出てくる悪魔像(現在、ルーブル美術館にある)は、古代メソポタミアの神パズズである。他にも「悪魔」にされた神々多数。
「魂」という概念を哲学の俎上に載せて、その存在の意識化に決定的な役割を演じたたのはソクラテス(紀元前470-399)であったと言われている。
古代のギリシア人たちは魂は肉体の消滅とともに消えてしまうという考えに依拠していた節がある。その代わりに、名声、栄光、名誉を「不滅」であるものと捉えていた。
そういうわけで、ギリシア人は政治や軍事に並々ならぬ情熱を燃やし死をもかえりみない勇敢な行為を成し遂げ「不滅」の名声を手に入れることに命をかける。
しかしながらソクラテスはそういう名声などはすぐに消えてしまうものであり、魂こそが「不滅」であると言い出したのだから、きな臭い匂い空気が漂うことになる。
金も財産も欲しい。命も惜しい。死後の名声も手に入れたい。これらは人間にとって本当に大切なものではない、大切なのは魂への心配りであると言ったのだから、ギリシア人にとってはソクラテスは厄介者以外の何でもない。
「不正をされても不正はするな」とソクラテスは言う。不正をすることで自分の魂を傷つけることになるからである。魂に配慮すること、魂を知ることが自分自身をよく知ることであり、善悪の判断は外にあるのではなく自分の内面にあるということになる。
ソクラテスは、自分の生みの親であるポリスによって不正な死刑宣告を受ける。クリトンなどの友人に脱走を勧められるが、それは不正をすることであり、断固拒否し自ら死に向き合う。
ただ「生きる」のではなく「よく生きる」ことが人間には最も大切であるというのがソクラテスの主張であり信念である。
私たちは日々目の前の事柄の処理にあくせくして、肝心なことには目をつぶって生きているので、時に自身が享受しているライフスタイルの吟味が必要なのかもしれない。
結局のところソクラテスは、その死によって魂の「不滅」だけではなく、その名声の「不滅」をも獲得したことになる。
と、そのようなことを最近おもしろいなあと思ったアニメ『不滅のあなたへ』という作品を観て思いました。
注)『不滅のあなたへ』は、ギリシア哲学のお話ではありません。現在、NHKにて毎週月曜日22:50放映中。
ローマのストア派
ローマのストア哲学
古代ギリシアのアテーナイでストア哲学は誕生する。紀元前300年。
「哲学」はあまり人気がない。「哲学」という堅苦しい日本語が事態をより悪くしているのかもしれない。明治時代に西周またはその周辺の人がギリシア語の「フィロソフィー」を日本語に移す際に、この「哲学」なる訳語が生まれた。
「フィロソフィー」の成り立ちは「フィロ(愛する)+ソフィー(知恵)」であり、そのままの訳語だと「愛知」とか「愛智」になってしまってなんだか格好がつかなかったのだろうか。
本家ギリシア語の「ピロソピア」という単語は「三平方の定理」などで有名なピタゴラス(紀元前582〜496) によって作られたとされている。
日本語でよく「自分に厳しい」の意味で「ストイック」という語が使われるが「ストア派」が語源である。
さて、「ローマのストア派」に辿り着くまでに簡単に時代の流れと有名な哲学者を整理してみよう。
まずはギリシアへ。
古代ギリシアにおいて記録に残る最古の哲学者がタレス(紀元前624頃〜546頃)で「万物の根源は水」と考えた。その弟子がアナクシマンドロスで「万物の根源は無限なるもの」とした。その弟子がアナクシメネスで、「世界の原物質は空気」と考える。
さらに原子論のデモクリテス(紀元前460頃〜370頃) 、「万物流転」のヘラクレイトス(紀元前535頃〜475頃)などが人口に膾炙している名前。これらの哲学者の関心は専ら「自然」へ向かっていた。
私たち自身の内にある「魂への配慮」が大切と考えたソクラテスの登場以来、哲学が急に「人間的」になってきたようだ。ソクラテスが死刑宣告を受け毒杯を仰ぐのが紀元前399年。
ソクラテスの弟子がプラトン であり、プラトン の弟子がアリストテレスである。アリストテレスを家庭教師として幸運にも迎えたのがアレクサンドロス大王である。
そのアレクサンドロス大王が急死するのは紀元前323年で、それ以降はヘレニズム時代と呼ばれる。
この時代のギリシア語はコイネー(共通語)と呼ばれ、当時の国際語になっていく。今で言えば英語と同じような地位である。
ストア派に目を向けてみよう。
ストア派の始祖とされるのはゼノン(前335〜263頃)である。そのゼノンの弟子たちも、またその弟子たちもたくさんいるわけだが、著作が悉く失われ、後世の著述家によって部分的に「誰々は〜のように言った」のように引用されている箇所を見つけられるだけである。そしてその教えはローマに伝わる。
ストア派哲学の教えを簡単にまとめると、自然と調和して生きることによって幸福に到達するという教えを基に、苦難に遭遇しても冷静沈着、平常心を保ち、富や名誉や快楽に無関心、無感覚であり、自制心や忍耐力を鍛える実践的な哲学であると言えるであろう。
漸く私たちの目的地であるローマに到着。この地で3人のストア派哲学者に会って、彼らの言葉に少しだけ耳を傾けてみよう。
1) セネカ(紀元前4〜後65)
2) マルクス・アウレリウス(121〜180)
3) エピクテトス(50頃〜135頃)
1) セネカ
ローマ属州のヒスパニアに生まれる。政治家であり、哲学者であり、戯曲も書く。ローマ皇帝ネロの家庭教師でもあった。
「生きることの最大の障害は希望を持つということであるが、それは明日に依存して今日を失うということである。」
「運命は、志あるものを導き、志なきものをひきずっていく。」
「どんな豊かな土壌でも、耕さなければ実りをもたらさない。人の心も同じである。」
「貧しい者とは、ほとんど何も持っていない人間のことではなく、もっと多くを渇望する人間のことを言う。」
2)マルクス・アウレリウス
貴族の家系に生まれる。いずれは皇帝になる定めがあった。エピクテトスの本を耽読してストア哲学へ傾倒する。後にローマ皇帝となる。五賢帝のひとり。戦地にて本を書く目的ではなく、自分のために内省しながら言葉を綴ったのがいわゆる『自省録』。
「人生において君を守るために付きそってくれるものは何だ?たった一つ、哲学だけだ。」
「恐るべきは死ではない。真に生きていないことをこそ恐れよ。」
「良い人間のあり方を論ずるのはやめにして、そろそろ良い人間になったらどうだ。」
「空中に投げられた石にとって、落ちるのが悪いことではないし、昇るのが良いことでもない。」
3) エピクテトス
奴隷として生まれる。後に解放奴隷となり、さらに哲学者となる。マルクス・アウレリウスとは現実的生活において対照的であるが、ストア哲学によれば、自分が生まれた境遇は精神の自由とは関係ない。社会的地位や財産がいくらあっても、人は自分の力を超えた運命によってあっという間に奈落の底に突き落とされる。
「逆境は人の真価を証明する絶好の機会である。」
「哲学とは、自分の幸福が外からの事柄にできるだけ左右されないように心がけて生きることである。」
「もし君が自分のものでないものを望むならば、君自身のものを失うことになる。」
「幸福への道はただ一つ。意志の力でどうにもならないことは悩まないことだ。」
◯読書案内(それぞれ1冊ずつ)
セネカ
『生の短さについて 他ニ篇』
大西英文訳 岩波文庫
マルクス•アウレリウス
『自省録』神谷美恵子訳 岩波文庫
ヘラクレイトス
『人生談義(上・下)』國方栄ニ訳
岩波文庫
上記3人の中では、セネカが日本でも欧米でも人気があり、よく読まれている。元の言語はラテン語で書かれている。
『自省録』の日本語訳は4つくらい出ているが、神谷美恵子の日本語がわかりやすい。マルクス・アウレリウスのギリシア語は翻訳するのに骨が折れると思うけど、彼女は赤ちゃんを育てながら台所で翻訳したという逸話がある。精神科医でもあり、美智子皇后の相談役であった。尚、第1章は飛ばして2章からどうぞ。
『人生談義』は、エピクテトス自身が著したのではなく、弟子のアリアノスがエピクテトスから聞いた言葉をそのままえ書きとめた謂わば講義ノート。
言語と文字の関係
言語と文字の関係
たとえば日本語を全てアルファベットで表記してみて、横書きにして本を出版してみる。電車の中でその本を読んでいると隣の人に声をかけられ
「英語ですか?」
「いや日本語ですよ。」
「は?」
日本ではアルファベットで表されていると、何でも英語に思われてしまう傾向がある。外国語と言えば英語が幅を利かせている。
注) ここでのアルファベットは、ラテン文字のことであり、すなわちローマ文字のことであり、一般にローマ字と言われている文字を指す。
日本で暮らし日本語基準で考えると、私たちは言語と文字の関係性に気づかないことが多く、言語と文字を同一のものとして勘違いしたままであったり、あるいは靄がかかっているようなことがある。
文が、ひらがな、カタカナ、漢字で表記されていたら、それは日本語であろう。
ハングル文字で表されていたら、それは朝鮮語(韓国語)であろう。
いわゆるローマ字で書かれていたら、それは英語であろうか?
ラテン語や英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語などは、多少のバリエーションを含むが、ローマ文字で書かれる。先にも触れた通り日本語も頑張ればローマ文字で表現できる。Ganbareba dekiru to omou. Demo yominikuidesu.
古代のメソポタミアでは、楔形文字を使って、シュメール語やアッカド語、またインド・ヨーロッパ語であるヒッタイト語が表された。
インドで使われているデーヴァナーガリー文字を使って、サンスクリット語やネパール語やヒンディー語が表される。
ペルシア語はインド・ヨーロッパ語であるが、現在のペルシア語はアラビア文字を使って表現されている。古代のペルシア語は楔形文字を用いて表現されていたし、中世ではパフラヴィー文字が使われていた。
言語と文字の関係は、たとえるなら音楽と楽譜の関係と同じである。先ず音があり、その音を楽譜に表現する。同様に先に音声としての言葉があり、それを文字の中に閉じ込める。
もちろん文字のない言語も存在する。天才的なミュージシャンで実は楽譜が読めない人も少なくない。楽譜の読み書きができなければ音楽を作ることができないなどいうことはなく、文字がなくても言語は使用される。ただし、次の世代に情報を伝えるのに困難な場合がある。
その昔、ハワイでは文字がなかった。神々への信仰心や様々な体験などを後世に伝えるための表現としてフラ(フラダンス)が広まり、それは今に至っている。
オーストラリアの先住民族であるアボリジニ達は文字を持たなかった。そこで、重要な事柄をアートに託して後世に伝えるという手段を用いた。一般にこれはアボリジナル・アートと言われている。アボリジニについては「ドリーミング」という面白い概念があるのでGoogle先生に聞いてみよう。
今でも文字のない言語は多数ある。だからといってその言語が劣っているということにはならない。楽譜が読めないミュージシャンがそれ故に劣っているとはならないように。
言葉は、まず音としての言語が先にあり、その後に入れ物である文字にそれが詰め込まれていった。
そういうわけで言葉の学習において私たちにとって第一に発音を徹底する必要性が見えてくる。自分が作ることのできない音は識別できるわけがなく、いつまで聞いてもリスニングは聞き取れない。
これは勉強ではなく音楽と同じでトレーニングが必要となる。ヘタで構わない、完璧である必要もない、しかし少なくとも私たちはその理想に向けた努力はしてみても良いだろう。
ずっと音楽を聴いていれば、いつの日か練習をしなくても楽器が弾けるようになると思ってる人は流石にいないであろう。
語学は、トレーニングという観点では体育やスポーツとも似ている。練習せずにじっとテレビで野球を見ていれば、いつの日か野球が上手くなるだろうか?
私たちに必要なのは、ただぼっーと講義を聞くことではなく自分をトレーニングで磨くことである。語学は、他の教科とは異なり、音楽や体育と同じカテゴリーに分類されなけれならない。理論とトレーニング。
盲目の詩人や琵琶法師が長い詩を暗唱し朗誦することはよく知られている。文字がある故に私たちの記憶力は劣化したのだと言う人もいる。しかしながら幸運にも文字を持つ私たちはこれを有益に使いたい。
音楽家は慣れれば楽譜を見るだけで頭の中で音楽を鳴らすことができるように、書かれた文字だけを見て私たちは小説や哲学、詩やエッセイを享受することができる。
まずは音、次に文字。その次に数学的な文法理論が必要になり、これが確固たる自信に繋がる。そして言葉は現象を切り取り、時代を超えて、それを表現することができるようになる。これが他の動物と人間を区別している。