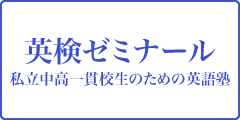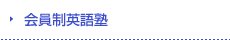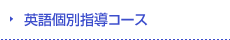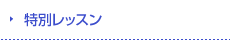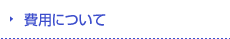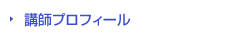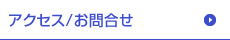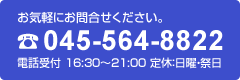Category
Archive

英語のリズム(encliticとproclitic)
英語のリズム(encliticとproclitic)
世界には多くの言語が存在し、その一つひとつに独自のリズムが流れている。その言語のリズムを無視し、母語のリズムで代用して話すことは、全く相手に通じないだけではなく、相手のリズムに乗れないことが聞き取りの不可能を引き起こす。
英語(ここではアメリカ英語を指す)は、ロックやジャズのリズムにあるような強弱アクセントが一定の間隔で現れる波のようなリズムで流れており、さらに音程における高低アクセントもそこに加わる。
一方の日本語は、5、7、5、7、7に代表されるように一音に一文字を当てて表現する。したがって英語下手な私たち日本人は、外国語の発音の際にも律儀に全ての文字に一音を当ててきっちりと発声する方が分かりやすいのではと思ってしまう傾向がある。
ここで紹介する考えは、古典語(ラテン語やギリシャ語など)を学習する際に現れるencliticとprocliticという考えを発展させたものである。簡単に言えば、ある単語は他の単語の一部であるように発音される、ということである。最も分かりやすい例から見ていこう。
「冠詞+名詞」の例
次のことを意識してみよう。
aやtheを入れても拍の頭を変えないようにする。
a, the, myなどは拍の頭ではなく名詞中心に発音する。
aやtheは早く弱く読む。
aやtheは、ターゲットの名詞の一部と意識する。
以下の練習をしてみよう。
練習1
手拍子と共に
パン!
パン!
パン!
パン!
one
two three four
dog
dog dog dog
a dog
a dog a dog a dog
練習2
パン!
パン!
パン!
パン!
dog
dog dog dog
the dog the dog the dog the dog
練習3
パン!
パン!
パン! パン!
apple
apple apple
apple
an apple
an apple an apple
an apple
このencliticとprocliticの考えを発展させていくと「リズムの等時性」という概念に行き着く。
英語音声学を専門にしている小川直樹先生によると、「リズムの強弱は等しい間隔で現れる。英語のリズムで最も特徴的な性質は、強勢の等時性である。つまり、文の発音上の長さは、単語数や音節数ではなく、強勢の数で決まる」ということである。具体例に触れてみよう。以下の英文の例は、『耳慣らし英語ヒアリング2週間集中ゼミ』(アルク、小川直樹著)から引用。
1. Cats chase rats.
2. The cats will chase some rats.
3. The cats will be chasing some rats.
先ず、1を3拍で発声してみよう。同時にタン、タン、タンと手を打ってみよう。
2も、このリズムを崩さずに声を出してみよう。大切なのは、タン、タン、タンというリズムに声を乗せることである。そうすると、theやwillやsomeを弱く速く読む必要が生じてくる。拍の頭をcats、chase、ratsに合わせることが大切。
3も、2と同様にcats、chasing、ratsに拍の頭を合わせる。他の語は飾りのようなものと割り切る。
もちろん単語一つひとつの発声を丁寧に習得することが先ずは大切になってくるが、同時に英語のリズムトレーニングが大切である。以下は、参考になる教材。
○『耳慣らし英語ヒアリング2週間集中ゼミ』(アルク、小川直樹著)は、本文中にも触れた教材。
○Carolyn Grahamという人は、英語のリズムをジャズチャンツという言葉で表現し、自らもピアノを弾いたりしながら英語のリズムトレーニングを行っている。多くのトレーニング本(cdも)も出している。children’s
jazz chants old and new, Oxfordなど。英語で歌を歌いたい人にも良い。
○現時点で、ある程度英語が聞き取れる人には、American accent
training, Barron’sがおすすめ。cdの説明も全部英語なのでどっぷり英語に浸かれる(疲れる?)。
○『英語の発音パーフェクト学習辞典』アルク。辞典と銘打っているが、英語リズムのトレーニング本である。
serendipityについて
serendipityについて
Sri Lankaのアラビア語名はSerendipというらしい。この単語に英語の名詞語尾を形成する-ityを付加するとserendipity(偶然に何かを発見すること)という英単語が形成される。
この有名な言葉を造語したのは、怪奇小説愛好家なら知らぬ者はいないホレス・ウォルポール(1717-1797)である。
ウォルポールの名を聞けば直ちに『オトラント城綺譚』が思い浮かぶであろう。この摩訶不思議な幽霊物語は今日のホラー小説の原点であると言って差し支えない。わが国では、名翻訳家平井呈一の手による日本語で、このghost storyを読むことができる。
ラフカディア・ハーンによると、昔のイギリス人(アングロサクソン人)は、神秘・超自然現象などを表すためには、このghostlyという言葉しかもたななっからしい。spiritやsupernaturalという単語はラテン語系である。
「人間のspiritが」とか「人間のsoulが」という代わりに「人間のghostが」という表現を昔のイギリス人は使っていたらしい。これに似ているのが古代ギリシャのダイモーンという概念である。
マルクス・アウレリウス の自省録の中に「その人の中のダイモーンが」というような表現が頻発する。実際に読むまではラテン語で書かれているものと早合点していたが、このローマ皇帝は、ギリシャ語で綴ったのである。1ページ読むのに数時間悪戦苦闘であるが、本はゆっくり読めば良いのである。
ダイモーンという表現は、個人の中に宿る「霊的なもの・精神・理性」のような意味で使っているような印象であり悪い意味は少しも感じられない。
後にこの「ダイモーン」は、プラトンの弟子のクセノクラテスによってマイナスの意味が付加され、その後はキリスト教の文脈において、悪の代名詞「デーモン」にまで降格されてしまった。
話を元に戻そう。
なぜ、serendipityなる英単語が、「予想外のものを発見したり、出会ったりすること」という意味になったのか?字義通りなら、せいぜい「スリランカ的なもの」の意味となる。
この語の由来は、ウォルポールが子どもの頃に読んだという『セレンディップの三人の王子たち(偕成社文庫、竹内慶夫編訳)』という物語に関係している。実際、書き出しを少し覗いてみよう。
「むかし、王たちがかしこく、重要な問題を話し合いによって解決していたよき時代のこと、セレンディップにジャッフェルという偉大な王がいた。王には三人の王子がおり、・・・」
物語を要してはいけないが、要するに、王は自分の国の後継者を決めるため、王子たちに諸国を遍歴させる。その間に様々なエピソードが挿入されている物語形式で「千夜一夜物語」のようなイメージ。偶然や才気によって、予期していないものを王子たちは発見していく。
「セレンディップ」第一のエピソードは、アメリカのテレビドラマ「メンタリスト」のジェーンを彷彿とさせる観察力で面白みがある。その他のエピソードは大したものではない。
この王子たちの旅を通しての「予期しない発見」をウォルポールは面白がり、自分自身の思いがけない発見を友達に説明するために、この物語の物語性を封じ込める目的 (このお話に出てくるあの感じだよ!という意味) でserendipという語を拝借し、serendipityなる言葉を作ってしまった。その英単語が21世紀にも生き残っているとは、ウォルポールも想像していなかったであろう。
serendipityの使い方については、アルキメデスの浮力の原理発見のエピソードやキューリー夫人の「偶然の発見」などを調べてみるのも面白い。
言葉と意識のピント合わせ
言葉と意識のピント合わせ
散々苦労して説明した挙句に、「一つ質問があるんですが、〜とは何でしょうか?」と今、説明したばかりのことを聞かれて唖然とした経験は、ある程度の人数の人を対象に教える仕事をしている人なら誰でもある。これは、ただ単に「あの生徒はきっとぼーっとしていたから」というぼーっとした理由では面白くない。
また逆に、先生側においては、自分は知ってると思っていることを生徒に質問されその問題を再認識し新しい発見をさせてくれた生徒に感謝することもあるであろう。ただし、普通は自分が分からない問題を質問されると先生は何故かすぐに怒ってしまう傾向があるものだが。
「人は見たいと思うものだけを見、聞きたいと思うものだけを聞く。」
目は開いていれば物が見えるし、耳は開いれば音が聞こえてくる。しかしながら、「ただ見えている、聞こえている」は、そのまま理解したことにはならない。意識のピントを合わせる必要があり、これが無ければ、本人不在で物事が右から左に流れていくだけである。
日本語で書かれている文章なら、そこに書き手の意図なり意味なりを即座に感じ取れるかもしれないが、同じ内容のものがアラビヤ文字またはデーヴァナーガリー文字(インド系)または、楔形文字(古代メソポタミア系)で書かれていたら、どうであろうか?
学習経験が無ければ、これらの文字は何かの模様にしか見えてこないであろう。まとまった意味ある文章が単なる模様と全く同じように認識されることになる。文字というものは氷山の一角であり、見えているものの下に意味が隠れている。
馴染みのない外国語の例は極端に響くかもしれないが、日本語で書かれたものから意味を感じ取ることも意識のピント合わせが必要で、これが無ければ、日本語で書かれた文字(漢字・ひらがな・カタカナ)もただの線の塊に過ぎない。
目で見る文字だけではなく、空間を飛び交う音としての言葉も、ピント合わせが無ければ、ただの雑音に過ぎない。
「人は見たいと思うものだけを見、聞きたいと思うものだけを聞く。」
書かれた言葉に意味を感じ取れるか、又はただの線の塊に認識されてしまうか、発せられた言葉に意味を感じ取れるか、又はただの雑音として処理されてしまうかは、私たち一人ひとりの意識のピント合わせ次第である。
道端に咲く小さな花にインスピレーションを感じ取る人もいれば、朝に鳴く小鳥の囀りに閃きを感じ取る人もいる。古い池の蛙にも意識は届く。
言葉から意味を感じ取れること自体、実はかなり特殊なことで、例えば知らない外国語のリスニングはどんなに頑張っても不可能である。知っているつもりの日本語も、意識のピント合わせが無ければ、つまり意識不在であれば、意味を感じ取ることができないと言える。
眠りたいのに眠れない時には、不得意な外国語の音声CDを聞くと良い。脳はたちまちシャットダウンし、すぐに眠れること間違いない。
ラテン語の語形成 No.1
ラテン語の語形成 No.1
形容詞から名詞へ(-tas, -itas)
liber(自由な) libertas
pauper(貧しい) paupertas
probus(正直な) probitas
benignus(親切な) benignitas
tranquillus(穏やかな) tranquillitas
callidus(狡猾な) calliditas
gravis(重い) gravitas
liveralis(寛大な) liberalitas
felix(幸福な) felicitas
celer(すばやい) celeritas
immortalis(不死の) immortalitas
suavis(甘い) suavitas
crudelis(残酷な) crudelitas
aequalis(同等の) aequalitas
言葉のプラシーボ効果
最近では、サプリメントなどで積極的な摂取が推奨されている亜鉛も少し前まで誤解の対象にされていたことがある。
亜鉛という物質は、鉛とは何の関係もないが、鉛という文字から受ける印象によって、何とはなしに体に害があるのではと思う人がいる。鉛=害。文字としての「鉛」も体には入れたくないという心理が意識下で働く。名称による風評被害が全く見えないところで発生する。
その逆に、私たちにはよく分からない「お経」だとか「祈りの言葉」といった「ありがたいお言葉」などは、物質的なものは存在しないにも関わらず人々に大きな影響を与えることがある。また、「酷い言葉」は、ナイフのように人を抉る。
プラシーボ効果の存在が、明確になりだしたのは、新薬の臨床試験の時だったそうである。患者のグループの半分には新薬を与え、もう半分には、プラシーボ(偽薬)を与える。新薬を与えた患者だけが病気の治療に成功するという見通しの実験であったが、結果は医者たちを当惑させるものだった。プラシーボを与えたグループも同様に病気が治ってしまったのである!
日本語のプラシーボという言葉は、英語のplaceboの音をそのままカタカナにしたものだが、語源はラテン語に行き着く。
現在形一人称単数形であるplaceo 「私は喜ばせる」を、未来形にするとplacebo「私は喜ばせるだろう」という形ができる。これが、私たちの知っている「プラシーボ」の語源である。ラテン語の発音は「プラケーボー」。
私たちの何らかの思い(思い込み)が、目から入るにせよ、耳から入るにせよ、口から入るにせよ、それはplaceboとなって、私たちの心や身体に侵入し、私たちの一部になって、私たちを「喜ばせてくれる」ことになる。